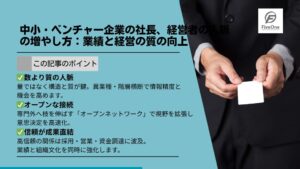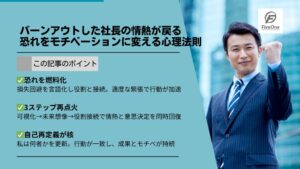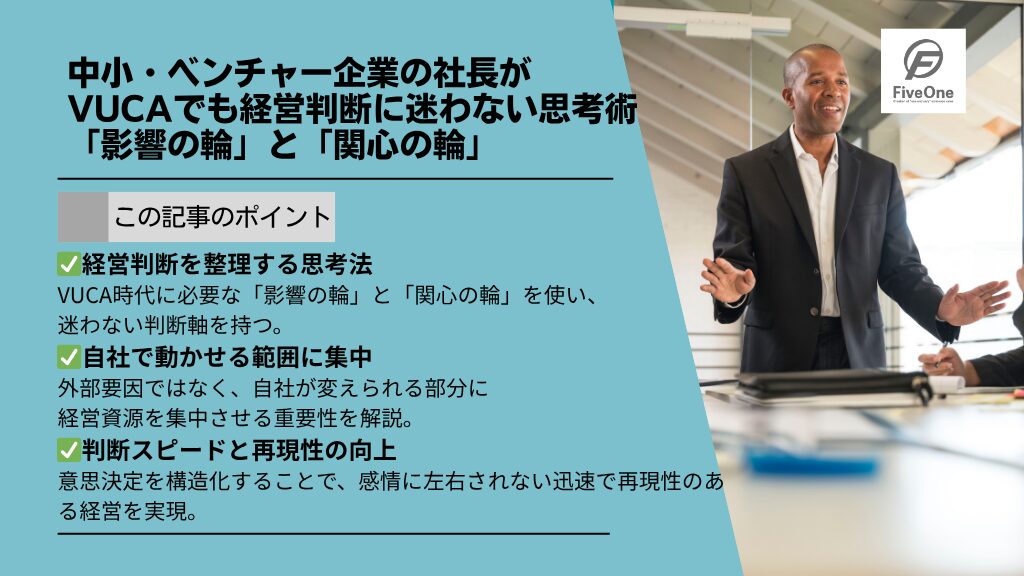
VUCAの時代、経営者の判断はこれまでになく複雑になっています。
私は中小企業の経営を続ける中で、為替や金利、地政学リスク、AI技術の急速な変化など、自分の力ではどうにもならない外部要因の多さを痛感してきました。
こうした不確実性の中で重要なのは、「何が起きるか」ではなく「自分が何を動かせるか」に焦点を当てることです。
スティーブン・R・コヴィー博士が説いた「影響の輪」と「関心の輪」は、混沌とした環境でも冷静に意思決定を行うための有効な考え方です。
本記事では、私自身の経営経験を踏まえながら、この2つの概念を経営判断にどう活かすかを解説します。
不確実な時代でも迷わないための“思考の軸”を、一緒に整理していきましょう。
この記事のポイント
- ✅経営判断を整理する思考法
VUCA時代に必要な「影響の輪」と「関心の輪」を使い、迷わない判断軸を持つ。 - ✅自社で動かせる範囲に集中
外部要因ではなく、自社が変えられる部分に経営資源を集中させる重要性を解説。 - ✅判断スピードと再現性の向上
意思決定を構造化することで、感情に左右されない迅速で再現性のある経営を実現。
第1章:VUCA時代に社長の判断が難しくなった本当の理由
経営判断が複雑化する背景
VUCAとは
- 変動性(Volatility)
- 不確実性(Uncertainty)
- 複雑性(Complexity)
- 曖昧性(Ambiguity)
を意味します。
私が経営に携わる中でも、この4つの要素は年々強まっていると感じます。
以前はデータや経験則に基づけば、ある程度の予測が立てられました。
しかし現在は市場の変化が早すぎて、過去の成功パターンが通用しません。
たとえば、数年前まで効果的だった広告手法が、今ではほとんど成果を上げないこともあります。
情報が多すぎる時代だからこそ、何を信じ、何を切り捨てるかの判断力が問われているのです。
「情報過多」が判断を鈍らせる
多くの社長は「情報を集めれば正しい判断ができる」と信じがちです。
私も以前はその一人でした。ところが、情報の洪水の中で本質を見失い、決断のタイミングを逃した経験があります。
特に中小企業はスピードが命です。100%の確証を待つより、70%の確信で動く勇気を持つことが重要だと気づきました。
完全な情報を追い求めることは、実は経営のリスクでもあります。
外部要因への過剰反応が経営を不安定にする
金利、為替、政治、国際情勢など、社長として気になる要素は多いですが、これらのほとんどは自分ではコントロールできません。
にもかかわらず、それらに神経をすり減らしてしまうと、判断軸が外的要因に支配されてしまいます。
私が大切にしているのは、「見通すこと」よりも「備えること」です。
動かせない要素に反応するのではなく、動かせる部分を設計しておくことが、ブレない経営判断につながるのです。
第2章:「関心の輪」にとらわれた経営はなぜ失敗するのか
「気になること」と「動かせること」は違う
経営者であれば、為替の変動や景気の先行き、競合の動向など、気になることは尽きません。
私も以前はそうしたニュースに一喜一憂していました。
しかし、スティーブン・R・コヴィー博士が言う「関心の輪」にあるものは、私たちが直接コントロールできない領域です。
そこにエネルギーを注いでも、状況が好転するわけではありません。
むしろ、他責的な思考が強まり、意思決定が遅れるリスクが高まります。
「外の世界」を追いすぎると社内が見えなくなる
外部環境の変化ばかりに目を向けていると、社内の変化を見逃してしまうことがあります。
たとえば、社員の意識変化や顧客ニーズの変動に気づくのが遅れると、内部の課題が積み重なります。
私は過去に「景気悪化」を理由に売上低下を説明していましたが、実際には社内の営業プロセスが古くなっていただけでした。
つまり、関心の輪にとらわれた経営は、原因を外に求めるあまり、自社の改善機会を逃してしまうのです。
「反応型経営」から「創造型経営」へ
関心の輪に支配された経営は、常に後追いになります。
VUCAの時代に求められるのは、反応ではなく創造です。
私は「起きたことに反応する経営」ではなく、「起こしたいことを仕掛ける経営」に変えてから、判断が驚くほど楽になりました。
関心の輪を見極めることは、経営の集中力を取り戻す第一歩です。
第3章:「影響の輪」に集中する経営者が結果を出す理由
「自分たちで変えられる範囲」に集中する
「影響の輪」とは、自分の意思と行動で変えられる領域を指します。
私はこの概念を知ってから、会議での議論や戦略立案の方向性が大きく変わりました。
以前は「業界全体の停滞」など抽象的な課題に時間を割いていましたが、今では「自社が動かせる範囲」に焦点を当てています。
たとえば、原価上昇を嘆くよりも、仕入れ先との取引条件を見直したり、在庫回転率を改善したりすることの方が現実的です。
こうした取り組みこそが「影響の輪を広げる」行動です。
意思決定のスピードが上がる理由
影響の輪に集中することで、経営判断の基準が明確になります。
私は会議で「これは自社で動かせることか?」と必ず問いかけています。
この一言があるだけで、議論の方向性が整理され、無駄な意見の応酬が減ります。
結果として、判断が早く、実行が速くなるのです。
中小企業においてスピードは最大の武器です。
影響の輪思考は、そのスピード経営を実現するための最もシンプルで強力なフレームワークだと実感しています。
「影響の輪」を広げることが経営の本質
経営とは、最初からすべてをコントロールすることではなく、「影響できる範囲を徐々に広げていくこと」だと私は考えています。
取引先、顧客、地域社会と信頼を築くほど、会社の影響範囲は自然と広がります。
影響の輪を広げるとは、事業を拡張することと同義なのです。
社長自身がその意識を持つことで、組織全体が前向きなエネルギーに包まれ、結果として成果がついてくる。
これは私が実際に経営現場で体験した、最も確かな実感です。
第4章:経営判断を迷わなくする「影響の輪」思考の3ステップ
ステップ1:課題を「関心」と「影響」に仕分ける
私は経営判断を行う際、まずすべての課題を「自社で動かせること」と「動かせないこと」に分けます。
たとえば、人材不足という問題ひとつをとっても、景気や人口動態は動かせませんが、採用方法や教育体制は自社で変えられます。
議論を始める前にこの線引きを行うだけで、経営会議の生産性が大幅に上がります。
これは「影響の輪」を明確にする最初のステップです。
ステップ2:動かせる領域にリソースを集中させる
経営資源は限られています。だからこそ、動かせる領域に人・時間・資金を集中させることが重要です。
私は常に「今週動かせること」「今期で成果を出せること」を明確にし、短期での達成を積み重ねる方針をとっています。
たとえ小さな成果でも、積み重ねが組織の勢いを生みます。
結果として、外部環境に左右されにくい経営体質ができあがるのです。
ステップ3:「撤退ライン」と「再挑戦ライン」を決める
私は判断を下す際、常に「撤退ライン」を明文化します。
どの条件を満たしたら撤退し、どの要素が改善すれば再挑戦するのかを事前に決めておくのです。
これにより、感情ではなくデータと条件で動ける経営判断が可能になります。
曖昧な状況で迷うのは、基準がないからです。
ルールを先に決めておけば、どんな不確実性にも冷静に対応できます。
「影響の輪」思考とは、行動と撤退の基準を自ら設計することなのです。
第5章:まとめ:VUCAでも迷わない経営者は「動かせる範囲」を知っている
VUCAの時代において、社長がコントロールできるものは限られています。
しかし、その限られた範囲を見極めて動かす力こそ、経営者の真価です。
私は「関心の輪」に囚われず、「影響の輪」に集中することで、判断のスピードも精度も上がりました。
どんなに不確実な環境でも、自分たちで動かせる領域に集中すれば、経営は安定します。
未来を予測するより、今を動かす。これが、迷わない経営者の共通点です。
最後に問います――あなたが今悩んでいるその課題は、本当にあなたが動かせることですか?
よくある質問(FAQ)
Q1:VUCAとは何ですか?
VUCAとは「変動性」「不確実性」「複雑性」「曖昧性」の頭文字を取った言葉で、現代の予測困難な経営環境を表す用語です。
Q2:「影響の輪」と「関心の輪」の違いは?
「影響の輪」は自分が行動で変えられる範囲、「関心の輪」は気になるがコントロールできない範囲を指します。経営判断では「影響の輪」に集中することが重要です。
Q3:経営判断に「影響の輪」を使うメリットは?
自社で動かせる要素に集中することで、判断のスピードと精度が上がります。迷いや過剰反応を減らし、経営資源を最適に使えるようになります。
Q4:中小企業でも「影響の輪」思考は有効ですか?
はい。むしろリソースが限られる中小企業ほど有効です。自社で影響できる領域に集中することで、経営の持続力が高まります。
Q5:「関心の輪」に時間を使ってしまう場合は?
「それは自分が動かせることか?」と問い直す習慣をつけましょう。会議や判断の前に仕分けるだけで、思考の整理とスピード改善が期待できます。