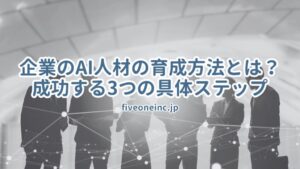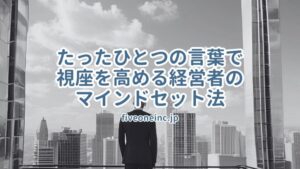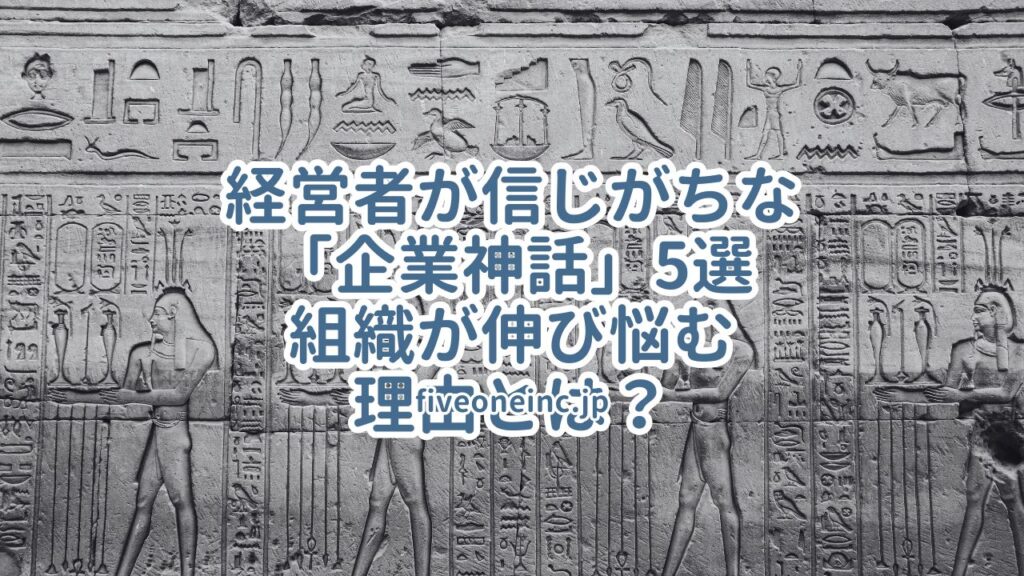
社員が思うように育たない、組織がうまく機能しない。
その原因は、経営者自身が無意識に信じている“企業神話”にあるかもしれません。
Forbesの記事「The Hidden Truths Of Corporate Life」では、現代の働き方における5つの誤解が紹介されています。
重要なのは、これらの神話が社員自身の思い込みではなく、会社の制度や組織文化そのものに組み込まれている場合があるということです。
特に中小・ベンチャー企業では、トップの考え方がそのまま評価基準や行動様式となり、組織の成長を止める要因となりえます。
本記事では、経営者が気づかず信じてしまっている5つの神話を取り上げ、組織づくりと人材育成に役立つ視点を提示します。
現場の頑張りだけでは組織は変わりません。経営の視点からこそ、変革は始まります。
- 働いた時間ではなく「成果」で評価する:長時間働く人が偉いという時代は終わり。成果と効率を重視した評価が社員の成長を促します。
- 昇進しなくても報われる仕組みをつくる:肩書きや役職だけに頼らず、専門性や実力を正しく評価する制度が必要です。
- 忠誠心より「市場で通用する力」を重視する:長く働くよりも、成長できる環境があるかが大切。社員を育てることが企業の強みになります。
1.「長時間働く社員=頑張っている」は危険な評価軸
時間で評価する時代は終わった
社員が毎日遅くまで残り、働いていると頑張っていると感じる経営者は少なくないかもしれませんが、今も「長く働く人は偉い」という文化が根強く残っている会社は多いでしょう。
しかし、時間だけを評価するのは危険です。
成果を上げる社員が正当に評価されないことが続けば、モチベーションが下がり、離職にもつながります。
事実、スタンフォード大学の経済学者ジョン・ペンカヴェル(John Pencavel)による研究(*The Productivity of Working Hours*, 2014)では、週50時間を超える労働で生産性が下がり、55時間を超えると労働時間を延ばしてもほとんど成果が増えないことが示されています。
またWHOも長時間労働の健康被害に警鐘を鳴らしています。
「長く働く」だけの評価は組織を歪める
つまり、時間をかければ良いという思い込みは今すぐ見直すべきです。
限られた時間で成果を出す社員に目を向ける評価が重要です。
長く働いているという理由だけで評価されるようでは、組織は歪みます。
評価制度を見直し、「成果」「工夫」「貢献」を反映させた多面的な評価軸へ移行すべきです。
限られた人材を活かすための制度設計
特に中小企業にとって、限られた人材をどう活かすかは死活問題です。
社員の健康や働きがいも含めて考えた評価制度こそ、企業の成長戦略の柱となります。
時間から価値へ、経営者の意識改革が求められています。
評価の見直しが未来をつくる
制度を見直すことで、現場が活性化し、優秀な人材が定着しやすくなります。
評価に納得できる環境を整えることは、離職防止にも直結しますし、採用にも良い影響を与えます。
成果を出す人が報われる組織であるために、時間ではなく価値基準を明確にしましょう。
経営の決断が文化を変える
時代は変わりつつあります。
経営者自身がその変化を受け入れることで、組織も進化するのです。
長時間労働から脱却し、真に生産的な働き方を推進する評価制度づくりを始めましょう。
それが社員と会社の未来を創る第一歩となります。
今こそ評価を変える時です。
社員は評価を見ています。
時間で測る時代ではもうありません。
結果とプロセスに目を向けましょう。経営の判断が組織の文化を変えていきます。その一手が未来をつくるのです。
2.肩書と給料が連動する評価制度は本当に機能しているか?
昇進すれば給料が上がる――その常識を疑う
あなたの会社では、昇進すれば自動的に給料が上がる評価制度になっていませんか?
確かにそれは長年続く伝統的な仕組みです。
しかし、この制度によって本当に人材の力を引き出せているでしょうか。
問題は、昇進=昇給というルールが、管理職としての適性がない人にも肩書を与える原因になっていることです。
昇進によって現場の優秀人材が崩れていく
プレイヤーとして優秀だった人が、マネジメント業務になった途端、能力を発揮できなくなるケースは珍しくありません。
逆に、組織全体に悪影響を与えるリーダーを生むことさえあります。
この背景には「給料を上げるには昇進するしかない」という構造的問題があります。
つまり、組織が一つのキャリアパスしか用意していないという点です。
スペシャリストとしての道を制度化する
これでは、専門職としてのスキルを深めたい人や、人を束ねるより現場に集中したい人のモチベーションが下がってしまいます。
そこで注目すべきは、「スペシャリスト型のキャリアパス」を明確に設けることです。
つまり、昇進せずとも給与や評価が上がる仕組みを整備するという考え方です。
多様な能力に報いる制度こそ経営者の戦略
技術、営業、広報、企画などの各専門分野において、深い専門性や実績を出す人にも、対価を支払う制度が必要です。
日本でも近年、職能資格制度やジョブ型制度を導入する企業が増えていますが、本当に重要なのは「人の強みをどう生かすか」という視点です。
「肩書と報酬の分離」が組織を強くする
すべての社員がマネージャー向きではありません。
それなのに、肩書を付けて責任を負わせることが、社員本人にも組織にも負担を与えてしまうことがあります。
評価と報酬の設計を多様化することは、組織に幅と深さを生み出します。
経営者は今こそ「役職」から自由な評価のあり方を考える必要があります。
昇進=成功という発想からの脱却
そうすることで、才能ある人が自分の強みを生かせる環境を整えられるのです。
昇進だけが成功という発想を手放すときです。
社員の多様なキャリアを支援する制度こそ、これからの企業には求められます。
3.「仕事だけできれば評価される会社」にコミュニケーションは根づくか?
成果さえ出せば良い—そんな職場に潜むリスク
あなたの会社では、成果さえ出していれば、それで評価される文化が根づいていませんか?
もちろん、結果を出すことはビジネスで最も重視される要素です。
しかし、それだけでは足りない時代になっています。
今の職場では、いかに周囲と関わり、協力し合えるかが大切です。
信頼構築と協力こそ、これからのビジネススキル
個人の力だけで成し遂げられる仕事は減り、チームで動く場面が増えています。
そのために必要なのが、コミュニケーション力や信頼構築力です。
これらも立派なビジネススキルとして評価すべきなのに、多くの企業ではまだ「仕事ができる=優秀」と捉えています。
無視される“見えない貢献”の積み重ね
結果として、内向的な人や一匹狼的な人が優遇され、周囲との信頼関係を築く努力が評価されない職場が生まれます。
しかし、長期的に見ればそれは組織にとって損失です。
連携不足、情報の断絶、部門間の対立など、問題が表面化しやすくなります。
協調性やフィードバックも“成果”である
こうした課題を防ぐには、コミュニケーション能力をきちんと評価する仕組みが必要です。
たとえばチーム内での協力姿勢、フィードバックの質、傾聴する姿勢など、数値化しにくいけれど確かな貢献を見逃さない制度が求められます。
部門連携と心理的安全性の評価へ
さらに、部門を超えた連携や共同プロジェクトの推進、メンタリングや育成など、信頼構築に寄与する行動も評価に含めたい項目です。
もちろん、定量的な成果とのバランスは必要ですが、人を動かす力は数字だけでは測れません。
“数字に表れない力”を評価できる組織へ
心理的安全性のある職場づくりには、人間関係に配慮した評価基準が欠かせないのです。
経営者は「仕事ができる」だけの社員像から一歩踏み出し、協調性や信頼関係づくりの力をきちんと評価に取り入れる姿勢が求められています。
そうすれば、個人の能力とチームの力が両立する強い組織が生まれます。
これからの評価制度には、数字に表れない価値を見抜く眼差しが必要です。
共に働くことの意義を見直すことが、組織の成長につながります。
4.「評価」は社内基準だけで決めていないか?市場価値を無視するリスク
社内評価だけで報酬を決める危うさ
あなたの会社の評価制度は、社内基準だけで成り立っていませんか?
「この部署での役割に対しては十分な給料だ」といった社内的な妥当性だけで判断していないでしょうか。
実はその考え方には大きな落とし穴があります。
なぜなら、社員の評価や報酬は、社内だけでなく「市場」における価値にも左右されるからです。
市場から見た「評価」とのギャップ
例えば、同じような職務を他社ではより高く評価していたり、逆に低い水準しか設定していなかったりすることもあります。
市場価値を無視して社内基準だけで給与を決めることは、人材の流出を招く大きな要因となります。
現に、優秀な人材ほど市場の相場に敏感です。
情報に基づいた納得感ある報酬へ
転職サイト、SNS、リクルーターからの情報などを通じて、自分の市場価値を把握している人も多いでしょう。
そうした中で、自社の評価が不公平に見えたり、業界水準と乖離していれば、不満や離職につながりかねません。
経営者が取るべき視点は、「この人に払うべき給与はいくらか?」だけでなく、「この市場での適正水準はいくらか?」という問いです。
外部データを報酬戦略に活かす
そのためには、外部データの活用が不可欠です。
業界別平均年収やスキル別相場などのデータベースを活用すれば、社員の報酬や昇給に現実的な根拠を持たせることができます。
また、採用時の条件設定にも活用すべきです。
自社の立ち位置を見直す材料にもなります。
市場と接続する評価制度へ
社内評価の整合性を保つためにも、市場視点での評価指標を補強することが求められています。
評価は「自社だけの正義」ではなく、「社会の相場」との整合性が問われる時代です。
公平な制度設計のために、外部の知見を経営に取り入れることが必要です。
社外の視点が組織の信頼をつくる
今後は報酬制度の見直しにおいても、社内外の情報バランスを重視する姿勢が不可欠です。
評価に客観性を持たせることが、優秀な人材の維持と獲得につながる鍵であり、組織の信頼性にも直結するのです。
5.「忠誠心が報われる」時代はもう終わった
勤続年数=評価の時代は終わりつつある
あなたの会社では、長く働いている社員を「忠誠心がある」と評価していませんか?
勤続年数を重視する考え方は、昭和の高度成長期から続いている伝統です。
しかし、時代は変わりました。
終身雇用や年功序列が崩れた今、忠誠心=評価という価値観だけでは通用しなくなっています。
古い価値観では若手が離れていく
特に若手世代は、「自分の成長が実感できない会社」から離れていきます。
それなのに、変化を拒み「会社に尽くせば報われる」という古い信念を掲げていては、優秀な人材ほど組織を去ってしまうでしょう。
また、長く働くことが評価される職場では、人材が固定化しやすく、組織の流動性が失われます。
求められるのは“どこでも通用する人材”
大切なのは、会社に長くいることではなく、「どこでも通用する力」を身につけているかどうかです。
スキル、思考力、対話力など、社外でも通じる能力を磨いている人材は、変化に強く、成果を出しやすい傾向があります。
こうした人材を育て、きちんと評価する制度が必要です。
「辞めたら損」という発想を手放す
一方で、企業としては「育てても辞められたら損だ」と感じるかもしれません。
しかし実際には、そうした人材が在籍していること自体が会社の信頼や成長力に直結します。
「この会社にいれば成長できる」と思われることこそが、採用にも好影響をもたらします。
“育てる企業”が選ばれる時代へ
優秀な人材を引きつけるには、自由と成長の両立が欠かせません。
経営者が考えるべきは、社員を囲い込むことではなく、「どこでも活躍できる人材」を育てることです。
それは結果的に、会社そのものの競争力を押し上げることにつながります。
忠誠心から信頼・成長への転換を
「辞めたら終わり」ではなく、「育てたことに意味がある」という発想の転換が必要です。
忠誠心だけに依存する組織文化を見直すことが、これからの時代の人材戦略に求められる視点です。
社員を縛るのではなく、伸ばす制度こそが信頼を生むのです。
まとめ:社員に成功させたいなら、幻想(神話)ではなく、戦略と現実を共有せよ
神話にすがる経営から、現実を見つめる経営へ
経営者として社員を成功させたいと願うなら、必要なのは神話ではなく現実です。
「長く働けば報われる」「肩書がすべてを決める」といった思い込みをそのまま評価軸にしていては、人材は本来の力を発揮できません。
神話にすがるのではなく、社員が自ら考え、動き、成長できる構造をつくることが、経営者の役割です。
第一歩は、評価制度の見直しから
その第一歩が、評価制度の見直しです。
時間や忠誠心ではなく、成果・貢献・協調性といった多面的な指標で見ることが大切です。
職場コミュニケーションの再設計
次に、職場のコミュニケーションを再設計すること。
心理的安全性のある環境なくして、信頼も連携も生まれません。
社外の視点を評価に取り込む
そしてもう一つが、社内だけで閉じない評価の導入。
市場や他社といった外部の視点を取り入れることで、報酬や役割の妥当性が高まります。
戦略で支える組織へ、明日から始めよう
構造を変えれば、社員の成長も組織の成長も加速します。
現実を正しく見つめ、社員を「幻想」ではなく「戦略」で支える。
それが今、経営者に求められている姿勢です。
まずは明日からできることに着手しましょう。
評価制度の見直し、コミュニケーションの再設計、外部環境との対話。
その積み重ねが、組織を変えていきます。
よくある質問(FAQ)
Q1. なぜ今、企業神話を見直す必要があるのですか?
現代の働き方や価値観は大きく変化しています。
かつての「長時間労働=頑張っている」「昇進=昇給」といった評価軸は、社員のモチベーション低下や人材流出の原因になりかねません。
時代に合った制度へのアップデートが、組織の持続的成長には欠かせません。
Q2. 具体的にどのような評価制度の見直しが必要ですか?
時間や肩書きではなく、成果、協調性、プロセス、専門性といった多面的な指標を導入することが有効です。
また、スペシャリストのキャリアパスや心理的安全性を重視した評価要素も併せて設計することで、社員の納得感と成長意欲を高められます。
Q3. 社内評価だけでなく市場価値も考慮すべき理由は?
社員は転職サイトやSNSを通じて、自身の市場価値を把握しています。
社内評価が外部水準とかけ離れていると、不満や離職のリスクが高まります。
業界相場などの客観データを活用することで、公平で納得感のある報酬制度が構築できます。
Q4. 組織内でコミュニケーション力をどう評価すれば良い?
チームでの協力姿勢、フィードバックの質、傾聴力など、定量化が難しいけれど重要なスキルを、マネージャーの観察や360度評価などを通じて可視化し、評価項目として組み込む方法があります。
これにより、協調性の高い行動が組織文化として育まれます。
Q5. 忠誠心よりも「どこでも通用する人材」を育てるべき理由は?
変化の激しい時代には、柔軟に対応できる人材こそが組織の競争力になります。
「外でも通用する力を持つ社員」を育てることで、結果的に会社のブランドや採用力、社員の定着率にも好影響を与えます。
社員を縛るのではなく、育てる戦略が重要です。