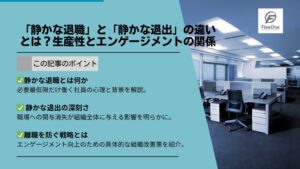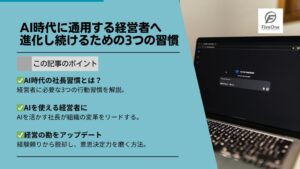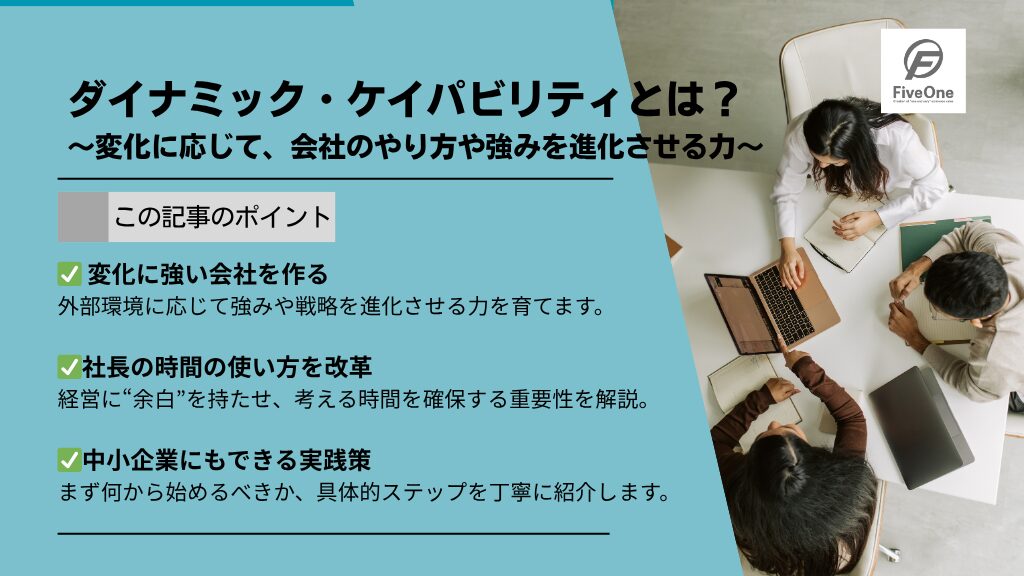
「ダイナミック・ケイパビリティ」という言葉をご存じでしょうか?
最近、経営学やビジネス戦略の分野で注目を集めているキーワードで、簡単に言えば「会社が時代の変化に合わせて自らを進化させる力」のことです。
急激な変化が続く今の時代。かつての成功が通用しなくなったとき、会社はどうすればいいのでしょうか?
そのヒントが、ダイナミック・ケイパビリティという考え方にあります。
この記事では、難しい理論をできるだけわかりやすく、中小企業の社長や経営者の方に向けて解説していきます。
「言葉は知らなかったけど、うちの会社にも必要かもしれない」と感じていただけるはずです。
変化に強い会社とはどんな会社か?
どうすればそうなれるのか?まずはダイナミック・ケイパビリティの基本から見ていきましょう。
この記事のポイント
- ✅ 変化に強い会社を作る
外部環境に応じて強みや戦略を進化させる力を育てます。 - ✅ 社長の時間の使い方を改革
経営に“余白”を持たせ、考える時間を確保する重要性を解説。 - ✅中小企業にもできる実践策
まず何から始めるべきか、具体的ステップを丁寧に紹介します。
ダイナミック・ケイパビリティとは?
ダイナミック・ケイパビリティの意味をやさしく解説
ダイナミック・ケイパビリティとは、時代の変化に応じて会社の「やり方」や「強み」を柔軟に進化させる力のことです。
もう少しかみ砕いて言えば、「今のままでは通用しない」と気づいたときに、新しいやり方を選んだり、今までの強みに頼らず別の道を切り開いたりできる力です。
英語では “dynamic capability” と書き、「動的な能力」と訳されます。
よく似た言葉との違い:「オーディナリー・ケイパビリティ」
ビジネス用語には似たような言葉もあります。
たとえば「オーディナリー・ケイパビリティ(Ordinary Capability)」という言葉は、日常業務を効率よくこなす能力のことです。
これは、今ある仕事を速く・正確にやる力です。
一方、ダイナミック・ケイパビリティは
- 「まったく新しい挑戦ができるか」
- 「変化にどう向き合えるか」
という点が本質です。変化を前提とした経営力、それがダイナミック・ケイパビリティなのです。
なぜ今この力が必要なのか?
VUCAの時代とは?
「VUCA(ブーカ)」という言葉をご存じでしょうか?
これは以下の4つの頭文字を取った、今の時代を表すキーワードです。
- V:Volatility:変化が激しくて(変動性)
- U:Uncertainty:将来が読めず(不確実性)
- C:Complexity;物事が複雑で(複雑性)
- A:Ambiguity:正解がわかりにくい((曖昧性)
つまり、先のことが読めず、状況はどんどん変わり、正解もひとつではない。
こうした環境で生き残っていくためには、企業も柔軟に形を変えていかなければならないということです。
「このままではまずい」に早く気づける会社が勝つ
かつて成功したビジネスモデルも、10年経てば陳腐化するのが当たり前の時代になりました。
変化が早いからこそ、企業もそのスピードに合わせて変わる必要があります。
特に中小企業は、組織の意思決定が速い分、早く動けばチャンスをつかめます。
しかし逆に、社長一人が抱え込んで動きが遅れると、すぐに時代に置いていかれるリスクもあるのです。
このような環境の中で「変わり続ける力=ダイナミック・ケイパビリティ」を持つことが、これからの会社経営において重要なカギになります。
ダイナミック・ケイパビリティの起源と背景
もともとは「資源ベース論」から生まれた考え方
ダイナミック・ケイパビリティは、1997年にアメリカ・カリフォルニア大学バークレー校の経営学者デビッド・ティース(David J. Teece)らによって提唱されました。
企業の競争優位性をどう維持し続けるか、というテーマから生まれた概念です。
当時は「資源ベース論(Resource-Based View)」が主流でした。
これは「他社にはない自社独自の資源や強みを活かすことが大事」という考え方です。
ところが、環境が急激に変わる中では、強みが“逆に足かせ”になることもあると分かってきました。
「変化できない強み」が弱点になる時代
たとえば、ある製品を高品質・低コストで作れるという強みがあっても、その製品自体が時代遅れになってしまえば意味がありません。
そのため、ただ強みを磨くだけではなく、状況に合わせて強みを作り替えること——それこそが「ダイナミック・ケイパビリティ」なのです。
中小企業にも必要な理由
変化が早い時代こそ「小さい会社のほうが強い」
ダイナミック・ケイパビリティは、大企業だけに必要な話ではありません。
むしろ中小企業やベンチャー企業のほうが、この力を活かしやすいとも言えます。
その理由は、「意思決定のスピード」です。
社長が現場に近く、すぐに方向転換できるのは中小企業の大きな強みです。
大企業のように複雑な階層や承認フローがない分、チャンスを逃さず素早く行動に移せます。
ただし、「社長の判断がすべて」だと危険
一方で、中小企業の弱点は「社長の時間と判断力がボトルネックになりやすい」点です。
社長一人にすべてが集中すると、変化の必要性に気づいても、そこからの実行が遅れてしまうことがあります。
だからこそ、会社として「自走できる仕組み」、つまり社長が全部を見なくても変化に対応できる体制づくりが重要なのです。
「社長が忙しい会社は変われない」という事実
“自由な時間”は贅沢ではなく、経営の武器
「毎日忙しく働いていることが経営者の役割だ」と思っていませんか?
実はこれは、今の時代には逆効果になることもあります。
社長があまりに忙しいと、外の変化に目が向かなくなり、必要な決断が後回しになります。
ダイナミック・ケイパビリティを発揮するためには、
- 「考える時間」
- 「未来を見通す時間」
- 「社員に任せる判断」
を確保する必要があります。
つまり、自由な時間は経営にとっての余白であり、武器なのです。
任せる経営が、会社の変化対応力を高める
忙しさから解放されるために大切なのが「任せる」ことです。
社長がすべての意思決定を握っていると、社員が自ら動けず、会社は硬直します。
逆に、権限を委譲していけば、社員が自分の頭で考え、スピーディーに動けるようになります。
これこそが、変化に強い会社づくりの第一歩です。
任せることはリスクではなく、成長のための投資なのです。
IBMに学ぶビジネスモデル変革の実例
「過去の成功」に固執しなかったからこそ、未来をつかめた
ダイナミック・ケイパビリティの理解を深めるには、実際に変化に成功した企業の例を見るのが一番です。
その代表的な事例がIBMです。
IBMはかつて、メインフレームコンピュータで世界を席巻したハードウェア企業でした。
しかし1990年代、IT業界の流れがパソコンとインターネットに移り、従来のビジネスモデルが通用しなくなりました。
業績が悪化する中で、IBMは思い切った決断をします。
ハードウェア中心のビジネスを縮小し、ITサービスやコンサルティング、ソフトウェア、後にはクラウドやAIへと事業を転換していきました。
これは「自社の強みを環境に合わせて進化させた」まさにダイナミック・ケイパビリティの実例です。
現在のIBMは“問題解決企業”へ進化
IBMは今や、企業の課題解決に寄り添うコンサルティング企業としても知られています。
AI「Watson」の開発や、Linux関連企業Red Hatの買収などもその一環です。
商品や技術そのものではなく、「顧客の変化するニーズ」に応える力を強化してきたのです。
この変化は、成功していた企業が「自分たちは変わる必要がある」と気づき、行動した結果です。
これは規模の大小を問わず、あらゆる企業に共通する教訓と言えるでしょう。
経営に“余白”を持つ社長がやっていること
忙しすぎる社長には、未来が見えない
ダイナミック・ケイパビリティを発揮するには、
- 「変化に気づく力」
- 「方向を選ぶ力」
- 「実行する時間」
が必要です。
そのためには、社長自身に“余白”がなければいけません。
朝から晩まで現場の確認、会議、承認業務に追われていては、変化を冷静に判断することができません。
実際に変化に強い会社の多くは、社長が「やらないことを決めている」ことが特徴です。
たとえば、定例業務は任せる、社外とのつながりに時間を使う、週に1日は“何も予定を入れない”時間を設けるなど、意識的に「考える時間」をつくっています。
任せることは「怠け」ではなく「戦略」
日本の経営者は「自分が動かないと会社が回らない」と考えがちです。
しかし、それではいつまでも会社は変われません。
任せるということは、組織の底力を高め、未来への時間を生み出す戦略的な行動なのです。
余白は、アイデアや判断を生み出す“土壌”です。
変化に備える経営とは、余白を恐れず、むしろ活かす姿勢から始まります。
自社の強みを「進化」させるための問い
「今の強み」は5年後も通用するか?
変化に強い会社になるには、自社の強みを「磨く」だけでは足りません。
「今のままでいいのか?」「この強みは今後も価値があるのか?」という問いを、定期的に投げかける必要があります。
実際、今ある強みが“足かせ”になることは珍しくありません。
成功体験に引っ張られて、新しい挑戦ができなくなることは、企業規模を問わず起こりうる問題です。
だからこそ、今の強みにこだわらず、常に「次の強み」を模索し続ける姿勢が必要なのです。
「変化に気づける経営体質」をつくる
強みを進化させるためには、以下のような習慣が効果的です。
- 定期的に市場環境や顧客ニーズを再確認する
- 異業種や社外の知見を取り入れる(社外取締役、顧問、経営コンサルタントなど)
- 経営幹部やチームに「変える自由」を持たせる
これらはすべて、「環境の変化に自ら気づける会社」になるための仕組みです。
強みは固定されたものではなく、時代に応じて変わっていい。そう考えられる会社が、ダイナミック・ケイパビリティを発揮できるのです。
具体的に何から始めるか?
1. 「経営に余白をつくる」仕組みを整える
ダイナミック・ケイパビリティを高める第一歩は、社長自身が“余白”を持つための環境づくりです。
まずは毎日の業務を洗い出し、「本当に社長がやるべきこと」と「他の人に任せられること」を分けてみましょう。
たとえば、顧客対応、経理処理、勤怠チェックなど、定型業務や繰り返しの業務は仕組み化・委任の対象です。
それによって確保できた時間は、
- 「今の経営を立ち止まって見つめ直すこと」
- 「信頼できる人と話すこと」
に使ってください。
日々の忙しさでは気づけなかった変化や課題が、ふとした対話や静かな時間の中で見えてくることがあります。
週に一度でもよいので、経営の方向性を見直す時間を確保してください。
そして、幹部や現場の社員、外部のパートナーとの対話を通じて、環境の変化や内部の課題を“社長だけで抱え込まずに捉える”習慣を持ちましょう。
2. 自社の「強み」「やり方」「組織」の3つを見直す
ダイナミック・ケイパビリティは、「今のやり方で本当に良いのか?」という問いから始まります。
以下の3点を見直すことで、自社にとっての変化への入り口が見えてきます。
- 強み:今うまくいっていることが、5年後にも通用するか?
- やり方:変化が起きた時、それに対応できる仕組みになっているか?
- 組織:社長以外のメンバーが、変化に気づいて行動できる状態か?
たとえば、ある会社では営業手法をすべてオンラインに切り替えたことで、遠隔地の顧客が増え、売上の地域バランスが一気に変わりました。
これも、社長が「このやり方のままでいいのか?」と問い直した結果です。
3. 小さな変化から「進化の習慣」を始める
重要なのは、いきなり大きく変えようとしないことです。
- 「月に1つ、社内のやり方を変えてみる」
- 「顧客との接点を見直す」
- 「外部パートナーの意見を聞いてみる」
など、小さな一歩を積み重ねることで、会社全体の“変化慣れ”が育っていきます。
ダイナミック・ケイパビリティは、決して派手な戦略ではなく、こうした「問い直し」と「行動の積み重ね」によって磨かれていくものなのです。
第11章:結論・まとめ
今、多くの企業が「予測不能な変化」の波にさらされています。
技術の進化、価値観の変化、人材の多様化、市場ニーズの流動性——これまでの常識がどんどん通用しなくなる中で、生き残る企業には共通点があります。
それは、変化に気づき、変化を恐れず、強みを“進化させる”ことができる企業です。
ダイナミック・ケイパビリティとは、まさにその力です。
変化を「脅威」としてではなく、「進化のチャンス」として捉えられるか。
成功体験に固執せず、「今のままでいいのか?」と問い直し続けられるか。
そして、その問いに対して、具体的に一歩を踏み出せるか。
中小企業であっても、いや、中小企業だからこそ、それが可能です。
この力は、突然手に入るものではありません。
社長自身が余白を持ち、考え、問い、周囲と対話し、そして動く。地道な積み重ねの中から、会社が“進化する力”を持ち始めます。
変化の激しい時代を乗り越えるために、ぜひ今日から「変化に応じて、会社のやり方や強みを進化させる力」を意識し、実践してみてください。
それが、次の成長につながる第一歩になるはずです。
よくある質問(FAQ)
Q1. ダイナミック・ケイパビリティとは何ですか?
A. 環境の変化に応じて、会社のやり方や強みを見直し、進化させる力のことです。
Q2. 中小企業にも本当に必要なのでしょうか?
A. はい。むしろ変化に柔軟な中小企業こそ、少しの工夫で大きな成長が見込めます。
Q3. 何から始めればいいのか分かりません。
A. まずは社長自身が「やらないことを決める」ことで、変化に対応する時間を確保しましょう。
Q4. 今のやり方でうまくいっているのに、なぜ変える必要があるのですか?
A. 今の強みが5年後にも通用するとは限らないからです。変化に備える力こそが持続的な成長を支えます。
Q5. 社員が変化に乗ってくれるか心配です。
A. 社員と共に考え、小さな変化から始めれば、徐々に組織全体が“変化に強い体質”へと育っていきます。