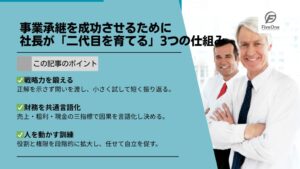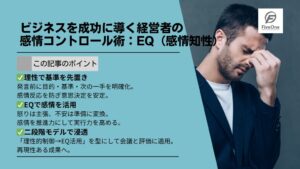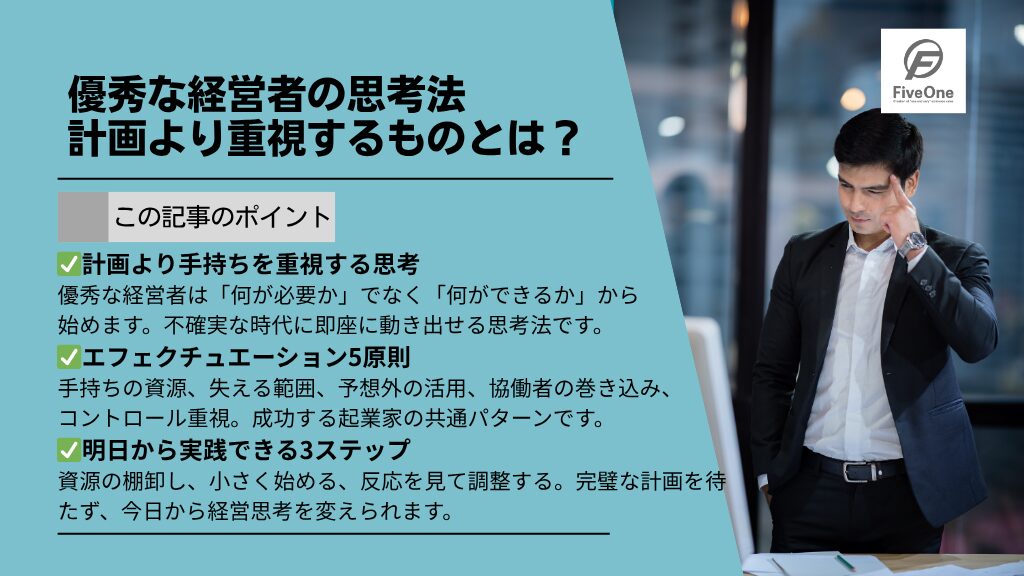
「計画通りに進めることが経営の基本」そう信じて、綿密な事業計画を立てる経営者は少なくありません。
市場調査を重ね、収支計画を作り込み、実行スケジュールを細かく設定する。
しかし現実は、計画通りにいかないことばかりです。
実は、優秀な経営者ほど「計画」以上に重視しているものがあります。
それは決して資金力でも、特別な人脈でもありません。
本記事では、成功する起業家が実践する「計画より大切にしている5つの思考法」を解説します。
この思考転換が、あなたの経営を変えるきっかけになるはずです。
この記事のポイント
-
✅計画より手持ちを重視する思考
優秀な経営者は「何が必要か」でなく「何ができるか」から始めます。不確実な時代に即座に動き出せる思考法です。
-
✅エフェクチュエーション5原則
手持ちの資源、失える範囲、予想外の活用、協働者の巻き込み、コントロール重視。成功する起業家の共通パターンです。
-
✅明日から実践できる3ステップ
資源の棚卸し、小さく始める、反応を見て調整する。完璧な計画を待たず、今日から経営思考を変えられます。
第1章:なぜ「計画重視」の経営がうまくいかないのか
多くの経営者が、事業計画の作成に多大な時間を費やします。
「3年後の売上目標」「市場シェアの予測」「必要な人員計画」。
しかし、どれだけ緻密に計画を立てても、現実はその通りには進みません。
理由は明確です。現代は不確実性の時代だからです。
新型コロナウイルスのパンデミック、急速なAI技術の進化、国際情勢の変動。これらは誰も予測できませんでした。
計画の前提条件が、数ヶ月で崩れてしまう時代に私たちは生きています。
さらに問題なのは、「計画を守ること」が目的化してしまうことです。
市場が変わっても、顧客の反応が予想と違っても、「計画に書いてあるから」と軌道修正できない。
この硬直性が、むしろ経営の足を引っ張ります。
では、優秀な経営者はどう考えているのでしょうか。
彼らは計画を軽視しているわけではありません。ただ、計画以上に重視しているものがあるのです。
第2章:優秀な経営者が計画より重視する5つのもの
世界的な経営学者サラス・サラスバシーは、優秀な起業家27名を対象に、彼らの思考プロセスを詳細に研究しました。
その結果、成功する経営者には共通する5つの思考パターンがあることが明らかになりました。
それは「計画」よりも、次の5つを重視するというものです。
①手持ちの資源を見る
優秀な経営者は「この目標を達成するには何が必要か」ではなく、「いま持っているもので何ができるか」と考えます。
これは「バード・イン・ハンド原則」と呼ばれます。
具体的には、
- 自分が誰なのか(スキルや経験)
- 何を知っているのか(専門知識やノウハウ)
- 誰を知っているのか(人脈やネットワーク)
から始めます。
新規事業を立ち上げる際も、理想の条件が揃うのを待つのではなく、手持ちのリソースから即座に動き出すのです。
②失える範囲を決める
計画型の経営者は「どれだけのリターンが期待できるか」を重視します。
一方、優秀な経営者は「最悪の場合、どこまでなら失っても大丈夫か」を先に決めます。
これが「アフォーダブル・ロス原則」です。
たとえば「この事業で3年後に1億円の売上を目指す」ではなく、「まず50万円だけ投資して、ダメなら撤退する」と考えます。
許容できる損失の範囲内で小さく始めることで、失敗しても会社は潰れません。
むしろ、失敗から学んで次の挑戦ができるのです。
③予想外を活かす
計画通りに進まないとき、多くの経営者は焦ります。
しかし優秀な経営者は、予想外の出来事を「チャンス」と捉えます。
これが「レモネード原則」です。
レモン(酸っぱい出来事)が手に入ったら、レモネード(甘い飲み物)を作るという発想です。
顧客からの予想外のクレームが、新商品開発のヒントになる。
想定と違う顧客層から注文が入り、新しい市場が見つかる。
計画に固執せず、サプライズを積極的に取り込むことで、当初は思いもよらなかった可能性が開けます。
④協働者を巻き込む
完璧な計画を一人で作り上げようとするのではなく、早い段階から周りを巻き込みます。
これが「クレイジーキルト原則」です。
クレイジーキルトとは、様々な布を継ぎ合わせて作るパッチワークのことです。
顧客、取引先、協力者から「一緒にやりましょう」というコミットメントを得ることで、手持ちの資源が一気に広がります。
そして協働の過程で、事業の方向性や目標そのものが進化していくのです。
「わからないから、一緒に考えてください」と言える経営者ほど、強いネットワークを構築できます。
⑤コントロールに集中する
計画型の経営者は、未来を予測しようとします。
しかし優秀な経営者は「予測できないなら、予測しなくていい」と考えます。
その代わり、自分がコントロールできる部分に集中するのです。
これが「パイロット・イン・ザ・プレーン原則」です。
飛行機のパイロットは、天候を変えることはできません。
しかし、刻々と変わる状況を見ながら、操縦桁を握って進路を調整し続けます。
経営者も同じです。市場環境は変えられなくても、自社の行動はコントロールできます。
状況を観察しながら、「いま・ここ」でできることに集中し、柔軟に舵を切り続けることで、望ましい結果へと導いていくのです。
第3章:「目標から考える」vs「手持ちから考える」思考法の違い
ここで、2つの思考法の決定的な違いを整理しましょう。
従来の経営思考と、優秀な経営者の思考は、出発点がまったく異なります。
従来型:目標から逆算する思考
多くの経営者は「達成したい目標」を最初に設定します。
「3年後に売上10億円」「市場シェア20%」といった明確なゴールです。
そこから逆算して、「そのために必要な資金は」「必要な人材は」「必要な設備は」と考えていきます。
この思考法は、環境が安定していて予測可能な時代には有効でした。
しかし不確実性の高い現代では、目標設定の前提そのものが崩れやすく、「必要なもの」を揃えている間に市場が変わってしまうリスクがあります。
新しい型:手持ちから広げる思考
一方、優秀な経営者は「いま持っているもの」から始めます。
自分のスキル、知識、人脈という手持ちの資源を起点に、「これで何ができるか」「誰と組めば可能性が広がるか」と考えます。
目標は最初から固定しません。行動しながら、顧客や協力者との対話を通じて、目標そのものを進化させていきます。
「計画を守る」のではなく、「可能性を創る」思考法なのです。
この思考転換が重要なのは、不確実な時代でもスピーディに動き出せるからです。
完璧な計画を待つ必要がなく、小さく始めて学びながら進めます。
そして予想外の発見を取り込みながら、当初は想像もしなかった成果へとたどり着けるのです。
第4章:明日から実践できる3ステップ
この思考法は、明日からすぐに実践できます。
以下の3ステップから始めてみてください。
ステップ①:手持ちの資源を棚卸しする
まず5分だけ時間を取って、紙に書き出してください。
- 「自分は誰か」(スキル・経験・強み)
- 「何を知っているか」(専門知識・業界情報)
- 「誰を知っているか」(取引先・知人・元同僚)
意外なほど、あなたにはすでに多くの資源があることに気づくはずです。
ステップ②:失える範囲で小さく始める
「最悪の場合、いくらまでなら失っても大丈夫か」を決めます。
そして、その範囲内で1週間以内にできることを1つ実行します。
完璧な計画は不要です。まず動いてみることが大切です。
ステップ③:反応を見ながら方向を調整する
行動したら、顧客や協力者の反応を観察します。
予想と違っても構いません。むしろ、その「違い」こそが新しい可能性です。
反応を見ながら、次の一手を柔軟に決めていきます。
目標も、必要に応じて進化させていいのです。
第5章:この思考法の正体「エフェクチュエーション」
本記事で紹介した5つの思考法は、「エフェクチュエーション」と呼ばれる理論に基づいています。
これは、米国バージニア大学のサラス・サラスバシー教授が、優秀な起業家27名の思考プロセスを詳細に分析して体系化したものです。
従来の「予測して計画する」経営学に対し、エフェクチュエーションは「コントロールして創造する」経営学と言えます。
予測できない時代だからこそ、この思考法が世界中の経営者から注目を集めています。
まとめ:計画は「作るもの」ではなく「創られるもの」
優秀な経営者が計画より重視する5つのもの。それは、
- 手持ちの資源
- 失える範囲
- 予想外の活用
- 協働者のコミットメント
- コントロールへの集中
です。
計画通りにいかないことを恐れる必要はありません。
むしろ、それは新しい可能性が生まれるサインです。
あなたの手持ちから始めて、周りを巻き込みながら、あなただけの経営を創っていく。
この思考転換が、不確実な時代を生き抜く力になります。
まずは明日、ステップ①の「手持ちの棚卸し」から始めてみてください。あなたの経営が、きっと変わり始めます。
よくある質問(FAQ)
Q1. エフェクチュエーションは既存事業にも応用できますか?
はい、応用できます。エフェクチュエーションは新規事業だけでなく、既存事業の改善や方向転換にも有効です。特に市場環境が変化している場合や、新しい取り組みを始める際に、手持ちの資源から始める思考法は既存企業でも大きな効果を発揮します。完璧な計画を待たず、小さく試して学ぶサイクルを既存事業に取り入れることで、スピーディな意思決定が可能になります。
Q2. 計画を立てることは無駄なのでしょうか?
いいえ、計画自体が無駄なわけではありません。エフェクチュエーションは「計画を否定する」のではなく、「計画に固執しない」ことを重視します。計画は方向性を示す道具として有用ですが、環境が変われば柔軟に修正すべきです。重要なのは、計画通りに進めることよりも、手持ちの資源で今できることを実行し、結果から学んで調整していく姿勢です。
Q3. 小さく始めると成長スピードが遅くなりませんか?
むしろ逆です。小さく始めることで、早く市場に出て顧客の反応を得られます。大きな計画を練って完璧を目指すよりも、小さく試して学習するサイクルの方が、結果的に成長スピードは速くなります。また、失敗してもダメージが小さいため、何度でも挑戦でき、最終的により大きな成功につながる可能性が高まります。
Q4. この思考法は誰でも実践できますか?
はい、誰でも実践できます。エフェクチュエーションは特別な才能や資金を必要としません。むしろ、リソースが限られている中小企業やスタートアップの方が実践しやすい思考法です。重要なのは「いま持っているもので何ができるか」と考える姿勢です。業種や企業規模に関わらず、この思考転換は明日から始められます。
Q5. 協働者を巻き込むコツはありますか?
最も重要なのは「完璧な計画を見せる」のではなく、「一緒に考えてほしい」と正直に伝えることです。「わからないから、あなたの知恵を貸してください」という姿勢が、相手のコミットメントを引き出します。また、小さく始めて実際に動いている姿を見せることで、協力者は安心して参加できます。リスクを最小限に抑えながら、一緒に可能性を探る姿勢が鍵です。