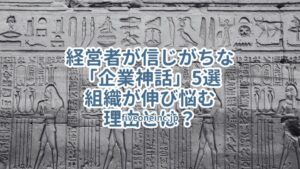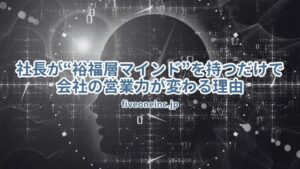経営者として日々の意思決定に悩んだことはありませんか?
その迷いの背景には、自分自身の「視座の高さ」や「感情の扱い方」が深く関わっています。
激変する市場環境、複雑化する組織運営、人間関係の摩擦─-こうした状況を乗り越えるために必要なのは、目先のテクニックではなく、本質的なマインドセットの再構築です。
本記事では、たったひとつの言葉を切り口に、経営者の視座を高めるための考え方・習慣・感情マネジメントの実践方法を、脳科学とEQ(感情知性)の観点からわかりやすく解説します。
- 視座を高めるには「言葉の力」を使え:感情や状況を正直に言葉にすることで、自分を俯瞰できる“高い視座”が身につく。
- マインドセットとEQは日常習慣で鍛えられる:1日5分の自己対話やセルフコーチングで、経営判断力と感情マネジメント力が向上。
- 迷ったらエグゼクティブコーチと視座を整える:ひとりで難しい場合は、プロの伴走者により視座のズレや思考の癖を可視化できる。
視座の高さが経営の質を決める理由
視点・視野・視座の違いとは
ビジネスの場面で「視点」「視野」「視座」という言葉が使われることは多いですが、それぞれの意味を明確に区別できている人は意外と少ないかもしれません。
- 視点とは物事を見る角度、つまり「どこを見るか」。
- 視野はその広がり、すなわち「どこまでを見ているか」。
- 視座とは、自分がどの立ち位置・高さから世界を見ているか、という「視る自分の立場」を指す。
経営においては、この「視座」が極めて重要な意味を持ちます。
たとえば、現場の課題を解決しようとする際に、視点だけが現場目線に固定されていると、全社的な方針や未来のビジョンと整合しない判断を下す危険があります。
逆に、高い視座を持つ経営者は、短期的な感情や個別の事情に左右されず、組織全体の構造や未来への影響を踏まえた意思決定が可能になります。
経営者にとっての「高い視座」がなぜ必要か
経営者の仕事は「複雑な情報の中から本質を見抜き、最終判断を下すこと」に他なりません。
その際、物事を狭い範囲や自分の経験則だけで捉えてしまうと、組織の未来にとって致命的な誤判断を引き起こす可能性があります。
視座を高く持つとは、目の前の現象だけでなく、その背景・構造・関係性までを俯瞰して捉える力を持つことです。
たとえば、人事における問題。
ある社員のパフォーマンス低下を個人の問題として処理するか、それとも組織風土やマネジメント構造の課題と捉えるかで、対応策はまったく異なります。
前者は短期的な問題対処に過ぎませんが、後者のように高い視座から本質的原因を捉えることが、経営の進化につながります。
視座が低いことで陥る判断ミスの典型例
視座が低いままで意思決定をすると、目先の成果や「感情」に流された判断が増えます。
たとえば、売上が落ちている部署にすぐにテコ入れを指示するが、実はその背景に中長期の構造的変化があることを見落としてしまう。
あるいは、社員とのトラブルで感情的に対応し、結果として信頼関係が破綻する──こうしたケースは、視座の低さゆえに全体像を見渡せなかった結果です。
経営者が自らの視座を高めるということは、「思考の土台」を高次元に置くことでもあります。
物理的に高い場所から町全体を見下ろすように、経営の全体構造・市場・組織・顧客・社員を統合的に見る力が、持続可能な成長戦略には不可欠です。
まずは、「自分は今、どの高さから物事を見ているのか?」と問いかけることが、視座を高める第一歩となります。
経営者に必要なマインドセットとEQ(感情知性)
マインドセットの定義と種類(固定型・成長型)
マインドセットとは、「物事に対する基本的な考え方・思考の枠組み」を指します。
経営者としての判断や行動の背後には、必ずこのマインドセットが存在しており、それが経営の方向性や組織文化を大きく左右します。
特に注目されているのが、スタンフォード大学の心理学者キャロル・ドゥエック氏が提唱した「固定型マインドセット」と「成長型マインドセット」(PR)です。
固定型は「能力は生まれつき決まっており変わらない」という信念に基づき、失敗を避ける傾向が強い。
一方、成長型は「能力は努力と学習で伸ばせる」と捉え、困難を学びの機会として受け止める姿勢を持ちます。
変化の激しい現代では、失敗を恐れず、柔軟に学びを重ねられる成長型マインドセットこそ、経営者にとって不可欠な思考基盤だと言えるでしょう。
EQとは何か?なぜ経営者に不可欠なのか
EQ(Emotional Intelligence Quotient)、つまり「感情知性」は、自分や他人の感情を正確に認識し、適切に対処する能力を意味します。
従来のIQが論理的・知的な能力を表すのに対し、EQは「人間関係」「共感力」「自己制御力」など、組織運営やリーダーシップにおいて不可欠な“人間性のスキル”を測る指標です。
経営者にとってEQが重要である理由は明確です。
リーダーの感情は、組織に波紋のように広がり、社員の士気や業績に直結します。
自分の感情を客観的に認識し、それに左右されずに意思決定できるEQの高い経営者ほど、冷静で信頼されるリーダーとなります。
また、社員の感情に共感し、適切なタイミングでサポートできるEQは、組織の心理的安全性を高め、パフォーマンス向上にも貢献します。
感情の言語化が自己認識と判断力を変える理由
EQを高める上で鍵となるのが「感情の言語化」です。
人間の脳は、言葉にすることで感情の正体を認識し、整理できるようになります。
心理学では「アフェクト・ラベリング(affect labeling)」と呼ばれ、脳科学的にもその効果は証明されています。
感情を正確に言葉にしたとき、扁桃体(感情の反応を司る領域)の活動が抑制され、前頭前皮質(論理的判断を担う部分)が活性化するのです。
経営者が「怒っている」「不安を感じている」といった内面を言葉にできるようになることで、自分自身を冷静に見つめるメタ認知力が養われます。
これは、衝動的な判断を避け、長期的・戦略的な意思決定を下すための土台です。
感情に流されずに判断できる力=高い視座を持つための基礎体力と言っても過言ではありません。
3. 視座を高める“たったひとつの言葉”とは
あなた自身の「感情を言葉にする」ことが、すべての起点になる
経営者として日々の判断を下す中で、焦りや不安、迷いを感じる瞬間は誰にでも訪れます。
そのときに重要なのは、自分の内面にある感情をきちんと捉え、それを「言葉」に変換することです。
たとえば「私は今、うまくいっていない」原文(“I’m not feeling okay”)といった一言。
これは多くの場面で紹介されている言葉ですが、必ずしもこのフレーズである必要はありません。
大切なのは、“自分自身が納得できる表現”で、今の感情や状態を正直に言葉にすることです。
- 「今は調子が悪い」
- 「少し不安がある」
- 「自分らしくない気がする」
など、どんな言葉でも構いません。
自分の感情を率直に認識し、表現することこそが、視座を一段高くする出発点となります。
視座を変えるきっかけとしての感情ラベリング
前章で紹介したように、感情を言葉にする「アフェクト・ラベリング」は、感情の暴走を抑え、思考をクリアにする脳科学的効果があります。
ここで注目すべきは、言葉にすることで「物事を俯瞰する力」が養われる点です。
つまり、視座が自然と高まっていくのです。
- 今、自分は何を感じているのか。
- なぜそのような感情になっているのか。
言葉にすることで、感情に支配される側から、感情を理解する側へと自分の立場が変わります。
これは、経営者が冷静な判断を下すための必須スキルです。
その言葉は、独り言か?それとも誰かに伝えるべきか?
自分の感情を言葉にする際に悩むのが、「それを他人に話していいのか?」という問題です。
特に社員や幹部の前でネガティブな発言をすることにはリスクも伴います。
経営者は組織の精神的支柱であり、その発言は想像以上に重く受け止められるからです。
ただし、近年の経営論や心理学では、「適切な自己開示」がチームの信頼構築に寄与することもわかってきました。
特に注目されているのが、「心理的安全性」という概念です。
これは、メンバーがミスや不安、弱さを率直に話せる環境のこと。
経営者自身が感情を冷静に整理し、必要に応じて開示する姿勢は、この心理的安全性を育む基盤となります。
ポイントは、“感情の吐露”ではなく、“冷静に整理された自己認識”として伝えること。
たとえば「今少し立ち止まって考えたい」といった表現であれば、弱さではなく誠実さとして受け取られやすくなります。
この言葉を誰に、どのように伝えるかは、場面と関係性に応じて慎重に判断すべきです。
ですが、「言葉にすること」は、独り言であっても組織にとっての最初の前進になります。
実践!視座を高く保つマインドセット習慣
1日5分でできる感情チェック&自己対話
視座を高く保つために最も効果的な習慣のひとつが、感情のセルフチェックです。
とくに忙しい経営者にとって、1日数分でも自分の心の状態を見つめ直す時間を確保することは、意思決定の質を左右します。
方法はシンプルです。毎日の終わりや始業前に「今、自分はどんな感情を抱いているか?」「なぜそう感じているのか?」と問いかけ、感じたことを一言でもノートやスマホに書き出すだけでOKです。
感情を表現する言葉が見つからないときは、「嬉しい」「焦り」「違和感」など、単語レベルでも構いません。
重要なのは、感情に“名前”を与えて意識化することです。
この習慣が、感情に飲み込まれずに経営判断を下すための基礎になります。
セルフコーチングに使える質問例
感情のチェックとあわせて取り入れたいのが、セルフコーチングです。
これは、自分自身に問いかけを行うことで思考の整理と視座の調整を図る方法です。
以下は、視座を高めたいときに有効な質問例です:
- この状況を5年後の自分はどう見るだろうか?
- 自分の反応は事実に基づいているか?感情に引っ張られていないか?
- 今の判断が、組織全体にどんな影響を与えるか?
- 自分の価値観やビジョンと、この行動は一致しているか?
このような質問を通じて、目先の感情や結果にとらわれずに「より高い立場」から物事を捉える力が養われます。
まさに視座を高めるマインドセットのトレーニングです。
感情・言葉・行動をつなぐ思考の習慣化
視座を一時的に高めるだけでなく、それを日常的に維持するためには、感情・言葉・行動の連動を意識する必要があります。
たとえば、「焦っている」と気づいたら、「なぜ焦っているのか」を言葉にし、「今できる最善の行動は何か?」を考える。
これをルーティンにすることで、感情に左右されない経営判断が可能になります。
重要なのは、感情の否定ではなく“共感と整理”です。
経営者にとって必要なのは、感情を抑え込む強さではなく、感情と向き合う柔軟さ。
日々の小さな自己対話の積み重ねが、視座の高さを維持し、長期的なリーダーシップ力へとつながっていきます。
とはいえ、自分ひとりでは気づきにくい感情の癖や思考の偏りも存在します。
そうした場合は、エグゼクティブコーチのような専門家の支援を受けて、感情・思考・行動を客観的に整理する時間を持つことも有効です。
信頼できる伴走者の存在は、視座を高く保つ大きな助けになります。
経営現場で使える「言葉のマネジメント」
社員との信頼構築に使える言葉の選び方
言葉は経営者の「行動の一部」であり、チームに与える影響は非常に大きなものです。
とくに社員との信頼関係を築くうえでは、日常的な発言の質が関係性を左右します。
命令口調や否定的な言い回しは、知らず知らずのうちに心理的な壁を生み出す要因になります。
一方で、「どう思う?」「あなたの視点を聞かせてほしい」といった問いかけ型の言葉は、対話を促進し、心理的安全性を育むことにつながります。
信頼は“強い言葉”で得るものではなく、“丁寧な言葉の積み重ね”で育てるものです。
経営者のひとことが、社員にとっての安心材料にも、圧力にもなり得るという前提を常に持っておきましょう。
苦しい局面で感情に呑まれずに判断する方法
経営には必ず、迷いや葛藤、プレッシャーを伴う局面が訪れます。
そうしたとき、感情に引きずられて判断してしまうと、後々に禍根を残す可能性が高くなります。
大切なのは、その瞬間に「自分は何を感じているのか?」と問いかける習慣を持つことです。
感情は消すべきものではなく、理解すべきものです。
たとえば「焦っている自分に気づいた」と言葉にするだけで、判断に必要な冷静さを取り戻せることがあります。
言葉にすることで感情を俯瞰し、その上で論理的な意思決定に移行する。
この流れを習慣化することで、感情に呑まれない経営判断が可能になります。
経営者自身のメンタルを整える“口癖”の力
日常的に使う「口癖」は、思考の質を左右する“マインドセットのスイッチ”のようなものです。
たとえば「まあ、なんとかなる」「今は一度止まって考えてみよう」といったフレーズは、ネガティブな状況でも心を落ち着かせる効果があります。
逆に、「どうせ無理だ」「また失敗した」などの言葉が習慣になっていると、無意識に自信や判断力を削ってしまいます。
言葉は思考をつくり、思考は行動をつくる──この流れを理解し、自分の口癖を意識的に選ぶことが、経営者としての感情マネジメント力を底上げします。
自分に語りかける言葉が変われば、視座も変わります。
だからこそ、日々の“つぶやき”を見直すことは、最も簡単かつ効果的なマネジメント手法のひとつなのです。
まとめ:視座・言葉・マインドセットが未来の経営を創る
言葉ひとつで世界が変わる
経営者としての視座を高める──それは、単に物事を俯瞰的に見るというだけでなく、自分の内面と深く向き合うことでもあります。
日々の感情を放置せず、正しく認識し、それを言葉にする力。
たったひとつの言葉が、自分自身の状態を整え、チームの空気を変え、未来の判断に新たな光を当てることがあります。
「今は調子が悪いかもしれない」「少し立ち止まって考えたい」──その一言が、自分を俯瞰する視座のスイッチとなり、無意識に陥りがちな思考や感情のループから抜け出すきっかけになります。
視座と言葉はつながっており、それをコントロールするには日々のマインドセットの習慣が必要です。
成長する経営者は「感情」と「言葉」を支配している
マネジメント能力が高い経営者ほど、感情に支配されるのではなく、それを理解し、制御し、言葉にして伝える力を持っています。
これは生まれ持った資質ではなく、日々の自己対話や習慣の積み重ねによって築かれるものです。
感情を整理する力、言葉を選ぶ力、自分の視座を問い直す力──それらが揃ったとき、経営判断に“迷いがない状態”を作り出すことができるようになります。
視座・言葉・マインドセット。この3つは、経営者が自分自身を成長させ、組織と社会にポジティブな影響を与えていくための、最も本質的な経営資産と言えるでしょう。
よくある質問(FAQ)
視座を高めるには何から始めればよいですか?
まずは「自分は今、どの高さからこの状況を見ているか?」と問いかけてみてください。感情を言語化し、ノートに書くなどの習慣が視座を客観視する第一歩になります。
EQやマインドセットは鍛えられますか?
はい、どちらも後天的に鍛えることができます。特にEQは、感情を意識的に捉える練習や、フィードバックを受け入れる経験を通して向上していきます。
社員に「うまくいっていない」と伝えるのはアリ?
伝え方次第です。感情の吐露ではなく、「整理された自己認識」として開示することで、信頼構築や心理的安全性の向上につながります。
感情の言語化に自信がないです。どうすれば?
「単語ベースで書き出す」ことから始めましょう。「不安」「焦り」「嬉しい」など、一言でもOKです。言語化は筋トレのように慣れで上達します。
ひとりで視座を保つのが難しい場合、どうすれば?
そのようなときは、エグゼクティブコーチなどの専門家に協力を仰ぐのが効果的です。
第三者の視点から感情や思考を整理してもらうことで、自分では見えなかった視座のズレや思考パターンに気づくことができます。
継続的に対話することで、マインドセットの強化と意思決定の質の向上をエグゼクティブコーチがお手伝いします。